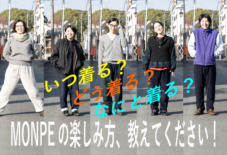【考えたこと】琉球絣の柄の特徴と、久留米絣に引き継がれている文脈。
【考えたこと】琉球絣の柄の特徴と、久留米絣に引き継がれている文脈。
琉球絣は1400年前後にはじまりました。絣の技術はインド発祥とされていて、沖縄には中国や東南アジアからその技術が伝搬しているとされています。そして、琉球王朝時代に御絵図帳という確率された柄見本帳がつくられ、今も、その柄をベースに琉球絣の図案は構築されます。面白いのは、その柄を絶対使わないといけないというルールがあるわけではなく、あくまでも先祖の方々、先代がそれをやってきたからという、引き継がれたなんとなくのルールを、今もみな守りながらやってるというのが現状で、なんだか、すぐ現代に合わせていろんな柄を構築してしまいそうなのに、そこをしっかり守りながらやる絣の工房の方々はすごいなと感心します。
また、久留米絣は1800年前後に発祥し、時代に合わせてどんどん柄のあり方や、また織り方は機械織と手織りを両方やったりと、その時代に合わせて変化をしていき、今も、柄はどんどん開発され、織元さんに行くと、新しい試みや柄の構築がどんどんされています。ただ、日本全体からみると、もちろん、なんでもありというわけではんく「久留米絣」というルールの中で、独自の開発がいろいろと行われているという感じです。
2月3日(土)から、琉球絣×久留米絣 クッション100展がはじまりますが、沖縄の琉球絣工房3人を迎えて、トークイベントも行います。伝統と現代の間で、今後未来をどうしようかと議論をしている最中です。その考え方などを聞ければと思います。ぜひ参加ください。
その他のお知らせ

【サラサラ派?ポツポツ派?】 糸で選ぶ久留米絣

【新商品】サイセーズ x yohaku ドバイパンツ

【季節のおすすめ】卒業・入学の節目、新しい門出に

【季節のおすすめ】冬から春まで使える、あったかくなるモノ

【お知らせ】 MONPE 価格改定について(2026年3月4日〜)

【新規掲載】白い常滑急須・TAKASUKE

【リクルート】 愛媛大洲店 店舗運営スタッフ(社員・パートスタッフ)募集 リクルート説明会開催(2月開催)