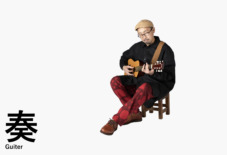【考えたこと】うなぎニョロニョロ。福岡県南筑後地方に軸足を置きながら、うなぎを食べながら考える。

あくまでも軸足は「ちくご」が中心。
それが、考えるきっかけになる。
昨日、久留米絣で鹿児島陸さんとのコラボの企画などを行っている、雑貨や服飾雑貨、自然派ワインやグロッサリーなど、ヨーロッパで作られている「最小単位のプロダクト」を中心に扱っている(説明が難しいのでHPより引用)東京・外苑前のdoinelの築地さんとご飯にいきました。いろんな方が毎日食事に誘ってくれて、お店をとってくれています。築地さんとは、うなぎだけにかわかりませんが、うなぎを食べにいきました。
いろんな人と話して、自分なりに考える事もたくさんあります。一つだけ言えるのは僕らの強みというか面白みというか(自分たちでいっちゃだめだけど)、そういうものはやっぱり地域をある程度限定しているということだと思います。そのことはうなぎの寝床についてという部分に書いています。今、少しずつコラボの話しや、先日行ったグアテマラの絣のことは、やっぱり僕らが住んでいる筑後地方を軸に考えている企画です。海外の技術や文化を学んで自分達の文化を見直すきっかけとなったり、現代に置いて取り入れなければならない部分は積極的に取り入れる。そういう姿勢が大事だと思っています。
外から学ぶべきことは学び、
取り入れるべきことは、取り入れる。
先日、インドの布の本をみたら、ある時代にはイスラム圏やトルコの方から腕のたつ職人をつれてきて良いものを、貴族階級の人(カーストの上の方)が作らせた。そして、技術が大幅に向上したということが書いています。時代は変わり続けていて、しっかり昔ながらのやり方を守って行きながら、新しい技術を取り入れたり、開発したりということが常に必要だと僕は考えています。
過去から現在、そして未来へ。
今、伝統工芸と呼ばれているものも、もともとは存在しなかったものだと思います(すごく古代から考えると)。開発された当時は劇的に斬新で新しいものだったのだと思います。それがある程度の規模になって名声を得出すとそれに固執して保守的になってしまう傾向があると思います。それは違って、やはり要素的なものや根本の考え方は残しながら柔軟に世の中に対応していく必要があると思います。そして、過去から現在を見て文化や技術を受け継いで行く部分。今から未来に対して新しい創造をしていく部分、両方考えながら前へ推進していく力が必要だと思います。
僕らは小さな組織ですが、それぞれの考え方や個人で、地域を眺め、それぞれの視点で、それぞれの能力を持ってその資源を現代に伝わる形にもっていければ良いなと考えています。その可能性はどこの地域においても無限にあると考えています。それを見つけることができるかどうかは自分達次第。「この地域には何もないもんね。」というのも自分達次第。しっかり目を見開いて感じながら良い資源を見落とさぬよう。地域の人ともコミュニケーションをとりながら進めていきたいと思います。ニョロニョロとどこの方向へ向かっていくのかはまだ見えていません。
白水
その他のお知らせ

MONPEとなにする? 【旅・探・話・読】

【新掲載】久留米絣の開襟シャツ&半ズボン

【意見交換会】 久留米絣がある風景を考える、壁紙制作を通して見えたこと (7/24)

【新作予告】 壁紙ブランド「WhO」とのコラボプロダクト(壁紙 & MONPE)

【第12回もんぺ博覧会】 次は産地「八女」! 7/24(木)〜

【メディア情報】 テレビ朝日「こんばんは、朝山家です。」へ衣装協力しました

【つくりて訪問記 / 後編】 祭と風習。地域に息づくしごと / 筑前津屋崎人形巧房のしごと展