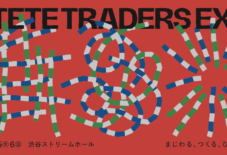【新商品】 Farmers’ MONPE 金井工芸 indigo × mud
 島の草木と泥。自然を借りる奄美の染色
島の草木と泥。自然を借りる奄美の染色
鹿児島・奄美大島の金井工芸は、1300年以上の歴史を持つ大島紬を染める「泥染」を担ってきた染色工房です。泥染は、島に自生する車輪梅(テーチ木)を煮出した染色液と、古代地層に由来する泥田を染め重ねることで染色します。
金井工芸では、泥染の基本である車輪梅×泥だけでなく、島で採れる様々な植物による草木染を掛け合わせた泥染にも取り組まれています。このMONPEでは、奄美の風土が生み出す色が重なり合って黒色ができあがる様子を、左右の染めを交差させることで表現して頂きました。
生地には愛知・知多半島の織物「知多木綿」を使用しています。久留米絣と同じ小幅のシャトル織機で織られており、ゆっくりと糸に必要以上の負荷をかけずにやわらかく織り上げています。型は「Farmers’ MONPE」で、ゆったりとしたシルエットです。
商品詳細はこちら
 Farmers’ MONPE 金井工芸 indigo × mud
Farmers’ MONPE 金井工芸 indigo × mud
39,600円(税込)
 「泥染」ってなんだろう?
「泥染」ってなんだろう?
泥染とは、奄美大島で行われている天然の染色技法です。奄美に自生する車輪梅(テーチ木)を煮出した染色液と、泥田の泥で染め重ねることで色を表現します。車輪梅に含まれるタンニン酸と、泥の中に含まれる鉄分(酸化第2鉄)が化合し茶褐色から黒色へと変化。大島紬では、これらの工程を80回以上重ねることで堅牢で深い黒を表現しています。
金井工芸のある龍郷町は、約150万年前の粘土地層から鉄分を多く含む泥が地表に分布しています。上流から水が注ぎ込みミネラルが滞留する山裾に泥田が作られ、その泥を使います。草木染めに使用する植物は自分たちで採集。島民の庭の剪定をしながら頂くこともあるそうです。
地表に現れた泥。自生する草木。泥染はすぐそこに、確かに存在する”自然”を借りることで営まれる染めと言えます。
詳しくはこちら(過去記事へ)
車輪梅はバラ科に属する常緑低木。奄美方言でテーチ木と呼ばれる。
採集した車輪梅。テーチ木染めは木の幹を使う。
木の幹をチップ状にし、10時間以上煮込む。煮込んだチップはそのまま次の煮出しの燃料になり、灰は藍立てや肥料になる。
車輪梅を煮出した染色液。発酵の具合によって泡の形が変わる。
車輪梅の染色液を鍋に注ぎ入れて揉み込む。3〜5分揉み込んだら石灰を加える。石灰は接着剤のような役割で、車輪梅染色液(酸性)と石灰(アルカリ性)が中和することで繊維に定着する。昔は石灰としてサンゴが使われた。
泥染をする泥田。
泥田の中には小さな生き物も住み着く。
泥染のあとは工房から車で10分ほどの川で水洗いを行う。染めから洗いまで、全ての工程があって奄美という土地の色ができる。
左右の染めが掛け合わさることで黒色を表現しています。