デニムの染め屋は未来が見える
ロープ染色のパイオニア
坂本デニム
このコラムは「Farmers’ MONPE 福山 両面起毛デニム」に関連した特集記事です。
後編はこちら
 Photo by Koichiro Fujimoto
Photo by Koichiro Fujimoto

生産量日本一のデニム産地、広島県福山市。福山ってどこ?という方も、実は知らぬ間に来ているのが、福山城。山陽新幹線の福山駅は日本一お城に近い駅で福山城の敷地内にあるため、電車で通過する度に訪れていることになります。
江戸時代、城下町の整備で広く土地が干拓されたものの、干拓地は塩分濃度が高く米づくりに不向きでした。そこで領主が綿花栽培をすすめた結果、福山エリアの南部は現在の繊維産地となっていったそうです。
今回訪問したのは、デニム糸の染色に特化した工場、坂本デニムさん。藍染工房として創業後、ジーンズのブームをきっかけに、独自開発のロープ染色*ができる機械を作り出したことから、青の濃淡〜草木染めのような茜色まで、他社にはできないさまざまな色彩で染色できるのが大きな強みです。
*ロープ染色
デニム特有の染色方法。ロープ状に吊るして、糸に張力を加えた状態で染めると、中心部が白く残り外側だけが染まる。
副社長の坂本磨耶さんは、「新色開発で先代をなかなか越えられないのが悩み。”色出しの変態”と呼ばれた会長が何千種類もの色をすでに世に出してきたので」と、誇らしさをにじませながら話してくれました。
「藍染に始まって、茜色に終わる。うちの会社のロゴマークは、まるで会長の生涯を象徴しているんです。亡くなる間際まで染料の新たな色出しに情熱を傾けていました」
坂本さんのお祖父様にあたる、会長が生涯をかけて追求して完成した草木染め風の茜色。ロープ染色でこの色を出すのはとても難しい。
 未来を逆算して染める!?
未来を逆算して染める!?
必然の色落ち
工場内で目にするものすべてが久留米絣産地のものと比べて大きく、生産量のスケールの大きさを感じます。工場内にはビームと呼ばれる、糸を巻く巨大な金属ロールがゴロゴロと転がっており、まるで自分がひとまわり小人になったような感覚に。
工程としては、ムラなく染めるため、整経という工程で糸をロープ状に巻き取り、屋根近く高さのある機械で糸を引っ張って張力を与えながら、染色槽を何槽も通して染めていきます。化学染料の中でも、インディゴ染色の難しいところが、空気に触れている間に色が変わっていき、その違いが温度によってもあってブレやすいので、3500mもの量を一気に染めています。一度染め始めたものを止めると失敗するため、お昼休みもノンストップです。染め上がり後は色の確認のため、500m間隔を色差系で記録を取って、数値で染まり具合を管理されていました。天然染料の藍染も、染めては引き上げて空気に触れさせる作業を繰り返して青の濃淡を生み出すことから、日本古来の藍染文化が今のデニム染色のベースにあることが、つながって見えてきました。
 染色工場が染色の際に考えるのは、どんな色落ちを目指すのか。ブランドよって目指す理想的な経年変化の姿は違うので、落ち方を逆算しながら濃度や染色方法を設計し、理想的な色落ちを染めの段階でつくり出しているそうです。私たちが日頃穿いているジーンズの色の変化は、使い方洗い方により濃度差はできるものの、あらかじめ染め屋さんの手で設計された、必然の落ち方だったのです!
染色工場が染色の際に考えるのは、どんな色落ちを目指すのか。ブランドよって目指す理想的な経年変化の姿は違うので、落ち方を逆算しながら濃度や染色方法を設計し、理想的な色落ちを染めの段階でつくり出しているそうです。私たちが日頃穿いているジーンズの色の変化は、使い方洗い方により濃度差はできるものの、あらかじめ染め屋さんの手で設計された、必然の落ち方だったのです!
 Photo by Koichiro Fujimoto
Photo by Koichiro Fujimoto
その後水洗い、乾燥させて、綺麗に糸を整列させた後、糊づけ機へ。何百もの糸を1本ずつ通していくのは完全な手作業で、見学時は髪の毛ほどの糸でされており、織機の幅も広いため見ていて気の遠くなるような根気のいる作業でした。
糊付け工程では、切り替えの際に機械が低速になり、その際に糊ムラができるので、前後20mくらいずつは毎回カットして使わないようにされています。もったいないように思いますが、糊のカスやムラが少しでもあると次に渡る織物工場が織る際の邪魔になるので、この部分の糸は出荷しないそうです。
出荷できない糸を、器用な職人さんがミサンガにしてサッカーイベントで配っている。他にも、活用の方法を模索中。
 Photo by Koichiro Fujimoto
Photo by Koichiro Fujimoto
「大量生産」も簡単ではない
見学を通して、「大量生産」という言葉の持つ、自動化された無機質なイメージが変わりました。デニムのように大量に効率よく生産できる大型設備を使うものづくりにも、人の判断や経験が入って手作業でされている部分は確実にあり、たくさんの量を同じ品質でつくることの難しさがあること。一度にばく大な量ができるため、ほんの少しの失敗であっても、ものすごい規模の損失になりますし、生産にあたる方は細心の注意を払いながら、つくることに向き合う必要が多分にあるのだと思います。
この数年でAIとの距離が急速に近くなり、なんでも出てきて相談できて、さまざまなことを簡単に知ったような気になってしまうのですが、言葉のイメージだけでぼんやりと捉えているものはそこら中にたくさんあって「実際」はどうなのかを知ろうとしたり、身体を使って、時間をかけて知ることをサボらないようにしたいものです。生身の人と会って、現場で見聞きして、においや音を感じてみてはじめて、記号のような情報が温度と手触りのある、生きたものに変わるのではないか。そうゆうものをおもしろく、誠実にお客さまに伝えられるお店であることができたらと思います。
田中
その他のお知らせ

【新商品】サイセーズ x yohaku ドバイパンツ

【季節のおすすめ】卒業・入学の節目、新しい門出に

【季節のおすすめ】冬から春まで使える、あったかくなるモノ

【お知らせ】 MONPE 価格改定について(2026年3月4日〜)

【新規掲載】白い常滑急須・TAKASUKE

【リクルート】 愛媛大洲店 店舗運営スタッフ(社員・パートスタッフ)募集 リクルート説明会開催(2月開催)
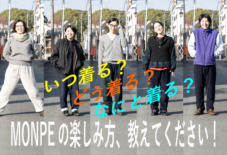
【アンケートご協力のお願い】MONPEの楽しみ方、教えてください!












