【仕入れのこと】 ぶどう畑からみえる「奈良」
【企画展】 奈良を編みとく 〜肌着・靴下・履物からみる奈良のものづくり〜 2025年 10/10(金) 〜 10/26(日)
 どうも、春口です。今回は「奈良を編みとく」と題して、靴下やレギンス、帽子、糸などの編みにまつわるものと履物を集めて、奈良のものづくりを紹介する企画展です。奈良といえば、東大寺の大仏や鹿、古代の歴史にまつわる観光名所的なところが真っ先にイメージされると思いますが、実は身近なところで目立たず日常を支えているものづくりが奈良にあります。その一部を紹介する機会です、ぜひ会場へお越しください。 さて、このコラムでは仕入れや各地を訪問する時に考えていることをつらつらと書いてみようと思います。
どうも、春口です。今回は「奈良を編みとく」と題して、靴下やレギンス、帽子、糸などの編みにまつわるものと履物を集めて、奈良のものづくりを紹介する企画展です。奈良といえば、東大寺の大仏や鹿、古代の歴史にまつわる観光名所的なところが真っ先にイメージされると思いますが、実は身近なところで目立たず日常を支えているものづくりが奈良にあります。その一部を紹介する機会です、ぜひ会場へお越しください。 さて、このコラムでは仕入れや各地を訪問する時に考えていることをつらつらと書いてみようと思います。
企画展詳細はこちら
環境によりけり
歴史は韻を踏む
先日久しぶりに奈良県に行ったのですが、改めてどういう土地なのかを調べるところから始めました。 今回に限らず、新しいものを仕入れて紹介する時は、その地域の歴史や土地の特徴、技術、素材、つくりての考え方などを意識しながら見ていきます。見た目や使用感、価格や機能面といったことは当然重要なのですが、うなぎの寝床ではそれとは別の側面からものを紹介することに主眼を置いています。ものの紹介は「地域文化をつなぐ」ために地域文化を表面化させる方法の一つと捉えているので、必ずしも買い物する上での物選びには必要ないであろうことも、なるべく多く、時にはやや過剰に伝えています。
まずはじめに全体像を捉えるために地図を見て、仕入れるものが生まれている土地の地形やその周辺の環境を確認します。平地と川、海、山の関係性を見たり、接している地域を見てて、自分が知っている土地や環境等と類似点がないかなども考えたりします。今回は葛城、大和高田、広陵を中心としたに中和地域と呼ばれる地域のものになるのですが、奈良盆地のことや、大和川という笠置山地(かさぎさんち)から奈良盆地、大阪平野を抜けて大阪湾の方へそそぐ川があるなーとか、俯瞰でみて調べます。地名などにもヒントがあります。例えば紺屋町、唐人町、鍛冶屋町、材木町などなど。これまでの経験上、日本各地で場所は違うけれど、やはり人と人、人と土地の関わりから地域文化が起きるので、時代に応じて同じような物事が各地域で発生していますし、その時代の流れが影響して、いろんな産業が生まれたり、成長したり、衰退したり、さまざまな変遷をたどって現代に続いています。それはどの地域も変わらないので、広く見てみると地域文化と呼ぶものが捉えやすくなると考えています。
中和地域の夕暮れ
とはいえ、どこかに調べ始めるヒントやきっかけがないかなぁと、まずはネットで検索するんですが、ネット上だけではもちろん辿り着けない情報がいっぱいあって、それを現地で車や電車に乗ったり歩いたりしながら各地を回り、キョロキョロとあたりを見ながら寄り道して、時には道の駅や観光案内所などでチラシをみて思考を巡らせて繋げていきます。訪問先のつくりての方達からもいろんな話が聞けるので、それでさらに理解を深めたり、その次につながる情報を得ていきます。
ものづくりの歴史の中には良い話ばかりでもなくて、いわゆる負の歴史と言えるような差別的なことも当然絡んでいることもあり、そのような時代を経て今に繋がっています。事実として見聞きしたものから理解を深めるヒントを得て、次の時代に向けて今を生きる人たちが取り組んでいること、地域文化との接点と思える営みを探して収集している感覚です。作家のマーク・トウェインの「歴史は韻を踏む」という言葉がありますが、まさにそうだなと思う話に巡り合う機会が多く、じゃあ次どうする?といった場面での選択や指針の持ち方、人間の思考の癖のような情報が見つかります。時代や場所や関係性など環境が変わっているだけで、人はあまり変わっていないのだなと。
 地域文化と換金作物
地域文化と換金作物
木綿畑から葡萄畑へ
今回訪問した足高メリヤスで、この地域の特徴が聞けないかと大阪から奈良に入る道中に目にした二上山(にじょうさん / ふたかみやま)あたりの葡萄の話をしてみたら、実はあの葡萄畑のところは元々綿花畑だったいう話が出てきました。葡萄を育てるのに土壌が向いていたからということで、全く想像していないことだったので綿と葡萄が繋がるのか!と驚きました。
奈良盆地は降雨量が少なく水が不足していたため稲作に制約があり、江戸時代から「大和木綿」と呼ばれる綿の栽培が盛んでした。明治になり海外から安価な綿が入ってきて衰退していき、その後は換金作物として果樹(葡萄、みかん)や野菜類が育てられはじめ、今に繋がっているようです。海外から安価な何かが入ってきて衰退する…あちこちの業界でよく聞く話だなとも思いながら、そういう状況を何度も乗り越えて今があるんだなと改めて思いました。
綿花が葡萄栽培に変わった話を聞いた時に、ふと私たちが拠点を置く八女とその周辺にも葡萄を作っているところがあるので、もしかしたら土壌が合うのは同じ条件だから過去には木綿を育ててた可能性もあるのかなぁなど想像しながら話を聞いていました。これは調べてみないと本当のところはわからないですが、そんなこんなで人と土地がどういう風に接していたかを知るきっかけなります。
殖産振興、技術の進歩、安価な輸入品、物流・情報のインフラの変化、感染症などなど時代によって大きく変化するきっかけが訪れます。その始まりが江戸なのか明治なのか、戦前・戦後なのか、平成、令和なのか。情報のインフラ、物のインフラ、資源と人の関わり、暮らし方はどうだろう。なるぺく視点を変えて、立体的に地域文化を探り紹介していけないかと考えています。
おしまい。
春口
<参考文献>
・大和川の歴史 / 大和川付替え300周年記念事業実行委員会
奈良といえば、鹿、大仏、だけじゃない。今回は奈良の「編みと履き物」に焦点を当てます。
奈良県は「靴下」の一大産地。国内生産量の約6割を占め、タイツやインナー、セーターなど、さまざまなニット製品の生産が盛んです。それだけでなく、長年日本の軒先で親しまれてきた近所履き「ヘップサンダル」も奈良。身近なところに「奈良」が隠れているのです。
靴下、インナー、カーディガン、サンダル、などなど。これからの季節にぴったりな奈良のものがずらっとナラびます。どうぞお越しください。
《開催概要》
奈良を編みとく 〜肌着・靴下・履物からみる奈良のものづくり〜
うなぎの寝床 旧丸林本家
2025年 10/10(金) 〜 10/26(日)店休日 火、水 (祝日営業)
時間 11:00〜17:00
住所 福岡県八女市本町267(会場アクセス)
電話 0943-22-3699
駐車場 あり
その他のお知らせ

【新商品】サイセーズ x yohaku ドバイパンツ

【季節のおすすめ】卒業・入学の節目、新しい門出に

【季節のおすすめ】冬から春まで使える、あったかくなるモノ

【お知らせ】 MONPE 価格改定について(2026年3月4日〜)

【新規掲載】白い常滑急須・TAKASUKE

【リクルート】 愛媛大洲店 店舗運営スタッフ(社員・パートスタッフ)募集 リクルート説明会開催(2月開催)
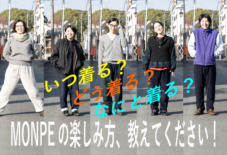
【アンケートご協力のお願い】MONPEの楽しみ方、教えてください!













